『コミュニティナース』 [地域愛]
内容紹介【Kindle Unlimited】
ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2018 を受賞 世界が注目する島根発、新しい地域ケアのあり方!
コミュニティナースという新しい働きかた・生きかたが、全国各地で始まっています。見守りや巡回など、さまざまな活動を通じて地域の人たちのそばで関係性を深め、安心を届けることで、健康的なまちづくりに貢献するキーパーソンです。 この活動を島根県でたった一人で始めた矢田明子さんと、全国に広がるコミュニティナースたちが取り組む、これからの地域ケアをめぐる奮闘記です。
ブータンを離任するまでの最後の3カ月間、早朝起きて夜明け前のヘリパッドを周回ウォーキングするのが日課となった。自分なりに健康状態をこれ以上悪化させないための措置で、薄暮で視界が限られる中、ポッドキャストでCOTEN RADIOを毎日1話聴くのが日課となっていた。そんな時に聴いたのが、本書の著者がゲストとして出られた3回シリーズだった。拝聴して、もうちょっと知りたいと思ったので、キンドルで探してダウンロードしてみることにした。
まだ読書スピードのリハビリが終わっていないため、集中力に欠けた散漫な読書になってしまったのは申し訳なく思う。機会があればまた読んでみたい。現時点で断定的なことは書きづらく、「要するに」というまとめをするのは失礼だとも思う。僕が知りたかったのは、①看護師をはじめとしたら医療資格を持っていないと「コミュニティナース」にはなれないのかということと、②僕が帰国して暮らしている地域にはコミュニティナースはいるのかということだった。残念ながら②については本書では紹介されていないのだけれど、①については看護師資格がないといけないわけではないということだけはわかったので、近くにコミュニティナースっぽい活動をされているコミュニティファシリテーターがいらしたら、「自分は自助具作製でお手伝いできます」とお伝えしておいて、何かの時にはお手伝いができるよう、知識と経験を深めておきたいと思う。
地域の人びとのふだんの何気ない会話や所作から、体の変調を察知するという能力は僕にはないけれど、地域の誰が何を知っているのかを知っていて、何かの時に誰をつないだらいいのかが判断できるのが大事なのだと僕は理解した。看護師免許や看護師としての勤務経験がなくても、近所で誰がそのような免許や経験を持っているのかを知っていたら、本書で描かれたコミュニティナースの活動は実現可能なのではないかと思う。本書は看護師経験者の視点で描かれているのでこういう書きぶりになるのだろうが、抱えていることはコミュニティでのファシリテーションそのもので、誰かが地域で活動していて、ケアのニーズに出会った時、それを地域の看護師経験者につなげてお助けを仰げればいいのだ。
いずれの場合であっても、出発点は地域の誰が何を知っているのかを知っているのが大事ということになる。僕が今勤めている会社を退職した後、どこで何をやろうとしても、これは必要なステップである。それに、僕が何を知っているのかを、周りの人びとにも知ってもらっておく必要も当然ある。
そう考えると、僕たちがコミュニティで暮らしていくのに、当たり前のように必要なことが書かれているのかなと思えてきた。
本書では上記②はわからないので、著者が立ち上げたコミュニティナースカンパニー(現在は株式会社CNC)のウェブサイトも見てみた。わりと僕の実家に近い地域でもコミュニティナース実践講座が開かれているのもわかった。残念ながら都合がつかないので講座受講というわけにはいかないのだけれど、冒頭の発言に戻るが、コミュニティナースが近くにいれば、「オレ、これなら手伝えます」と手を挙げられるようにはしておきたい。
『玉川兄弟』 [地域愛]
内容紹介【Kindle Unlimited】
【上巻】江戸は飲み水に不自由な土地であった。町の発展ひいては幕府の威令をいきわたらせるため、多摩川の水を江戸に曳くという壮大な計画が生れた。多摩川上流に生をうけた土木業者、枡屋庄右衛門・清右衛門兄弟は、目先の利益を排して見事入札に成功、数多の困難に立ち向う。若い兄弟の不屈の闘いをえがく歴史巨篇。玉川上水開墾に雄々しく立ち向かう若い兄弟の物語。
【下巻】江戸に生命の水を! 武蔵野の原野を貫く玉川上水開鑿に、若い兄弟は精魂を傾ける。しかし、自然の猛威はいたるところで牙をむき、計画の変更も余儀なくされ、遂には二人が師とも仰ぐ道奉行・伊奈半十郎の切腹にまで事態はいたる。彼らの無私の祈りは果して天に通じるか。……著者ならではの史眼が冴える感動巨篇。
このブログを2005年2月に開設して半年ぐらいした頃、一度だけ玉川兄弟を取り上げたことがある。長男が小学校になり、学校の授業で玉川上水のことは習ったらしいので、僕も一緒に勉強しておこうと、市立図書館の児童書のコーナーで玉川兄弟の関連書籍を借りて読んだ。当時はサンチャイ・ブログは読書ブログとしては確立していなかったため、何を読んだのかまでは記述がない。
玉川上水を取り上げるのはそれ以来となる。何をきっかけにして僕が初刊1974年という昔の作家の作品を取り上げたのかというと、その文庫版が講談社から1979年に出ていて、Kindle Unlimitedで読むことができるのを最近知ったからだ。何かの拍子に存在を知り、「読みたい本」のリストに載せてあったのだが、Kindle Unlimitedで読めると知るまでは、帰国した際に図書館で借りて読もうと漠然と考えていた。
ロックダウン中でもできること2 [地域愛]
これまでも何度も述べてきたことだが、今年に入って二度目の首都のロックダウンはさすがにこたえている。何もやっていないわけではないが、物事が前進しているという手ごたえもない。この状況でもやれることは何かと必死で考える毎日である。
年度末が近いこともあり、「これどうしたらいいか」「こういうのはできるのか」と自分の派遣元にロサの祭日の前に問い合わせたが、4日間なしのつぶてである。四連休だった当地の出先事務所は情状酌量の余地はあるが、東京の担当者がこの時期に照会事項を寝かせて週末を迎えたことには戸惑いが隠せない。「コロナ禍のメンタルヘルス」って、電話相談窓口に問い合わせをさせる前に、部署や事業所のレベルでやれることもあるのではないかと僕は思うが。
1人で悶々としているのは精神衛生上極めて宜しくないので、意識的にウェビナーに多めに出て、アンテナを張ったりするようにもしている。でも、受け身になるとウェビナーは意外と集中力が維持できない。そこで、単に後学のために聴講していて、他の出席者にほとんど知り合いもいない場合は、手書きでノートテイクをしたり、電子ホワイトボード「Miro(ミロ)」を使って議論を可視化したり、あの手この手で脳に記憶させるよう試みている。
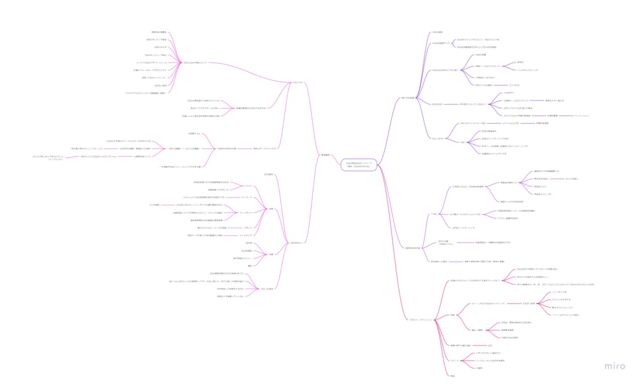
Miroは仕事で行うZoom会議の場でも先月あたりから使用を試行している。まだまだ使いこなせている感じはしないが、徐々に慣れていくしかないと思う。
年度末が近いこともあり、「これどうしたらいいか」「こういうのはできるのか」と自分の派遣元にロサの祭日の前に問い合わせたが、4日間なしのつぶてである。四連休だった当地の出先事務所は情状酌量の余地はあるが、東京の担当者がこの時期に照会事項を寝かせて週末を迎えたことには戸惑いが隠せない。「コロナ禍のメンタルヘルス」って、電話相談窓口に問い合わせをさせる前に、部署や事業所のレベルでやれることもあるのではないかと僕は思うが。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1人で悶々としているのは精神衛生上極めて宜しくないので、意識的にウェビナーに多めに出て、アンテナを張ったりするようにもしている。でも、受け身になるとウェビナーは意外と集中力が維持できない。そこで、単に後学のために聴講していて、他の出席者にほとんど知り合いもいない場合は、手書きでノートテイクをしたり、電子ホワイトボード「Miro(ミロ)」を使って議論を可視化したり、あの手この手で脳に記憶させるよう試みている。
《元々ノートテイクは多用。変えたのは書きやすいボールペン》
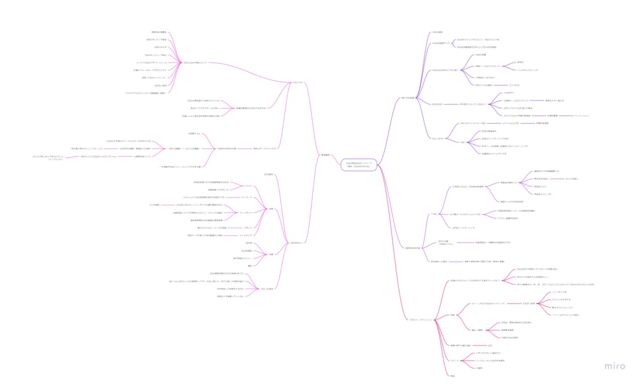
《あるウェビナーの内容をマインドマップに落としてみた》
Miroは仕事で行うZoom会議の場でも先月あたりから使用を試行している。まだまだ使いこなせている感じはしないが、徐々に慣れていくしかないと思う。
『南小国町の奇跡』 [地域愛]
内容紹介【購入】
地域が「変わりたい」という意思をもてば、奇跡は起きる!万年赤字の物産館がわずか1年で黒字転換、ふるさと納税寄付額は2年で750%増……DMO設立準備期から3年間、熊本県阿蘇郡南小国町に伴走してきた著者が語る、観光を軸としたヒトづくり、モノづくり、地域づくり。「南小国モデル」が今、明かされる。
今、経由地のデリー(!)の空港内ホテルに滞在中ですが、今朝自宅を出発する前に、2冊ほどKindleで購入しておいた本がある。優先的に読まねばならないのは既に160頁まで読み進めている別の本だが、読みにくいので進みが悪く、気分転換に別の読み物が欲しかったのだ。
それで先ずは羽田からデリーまでの約8時間の機中で、1冊読み切ることにした。それが、熊本県南小国町の地域おこしの経験について書かれた1冊である。
南小国町のことを知ったのは、トランスローカルマガジン『MOMENT』創刊号で、ファブラボ阿蘇南小国について紹介されていたからである。当然、本日ご紹介する本の中でも、ファブラボが出てくるものと期待していた。それが最大の理由だ。
そして、確かに紹介されてはいた。しかし、本書が取り上げる南小国町の地域おこしは、ファブラボよりも後にスタートした、もっと最近の出来事だった。
どら焼き再び! 伊吹堂の「池田のやま」 [地域愛]
最近、故郷である岐阜県揖斐郡の地元スイーツの紹介を立て続けに行なっているわけですが、今日はその続編です。
これから辛いものばかり食べなければいけない国に渡航し、下手したら2年間帰ってこれない可能性もある中で、このところやたらと口にしているのがスイーツ。しかも、餡子を使ったスイーツである。
どら焼きといえば、今のところ僕のイチオシはみわ屋(揖斐川町)の「こめどら黒胡椒バター」なのだが、このみわ屋の「こめどら」を意識してかどうかはわからないが、お隣りの池田町にある「伊吹堂」も、「池田のやま」という、バターを挟んだどら焼きを扱っている。
こちらの方は、「こめどら」と違って要冷蔵とは指定されていないが、過去の経験ではバターの硬さが確保できるぐらいには冷やしておいた方が歯ごたえがあっておいしいと思ったので、先日東京へのお土産で購入した際、食べる前に冷蔵庫で半日ほど冷やしてみた。
そうするといい感じで食べられて、家族みんなが「おいしい」「おいしい」と次々口にし、オヤジとしては面目を保つことができた。
実家での最終日の自由時間が30分ほどしかなかったので、揖斐川町のみわ屋まではとても行けず、「こめどら黒胡椒バター」は買って帰れなかった。実家から車で10分で行ける伊吹堂の一択になってしまったわけだが、「揚げパン」と「池田のやま」を大人買いして、お土産とすることができた。
こうしたジャパニーズスイーツが、これからしばらく食べられないのが本当に寂しい。
これから辛いものばかり食べなければいけない国に渡航し、下手したら2年間帰ってこれない可能性もある中で、このところやたらと口にしているのがスイーツ。しかも、餡子を使ったスイーツである。
どら焼きといえば、今のところ僕のイチオシはみわ屋(揖斐川町)の「こめどら黒胡椒バター」なのだが、このみわ屋の「こめどら」を意識してかどうかはわからないが、お隣りの池田町にある「伊吹堂」も、「池田のやま」という、バターを挟んだどら焼きを扱っている。
こちらの方は、「こめどら」と違って要冷蔵とは指定されていないが、過去の経験ではバターの硬さが確保できるぐらいには冷やしておいた方が歯ごたえがあっておいしいと思ったので、先日東京へのお土産で購入した際、食べる前に冷蔵庫で半日ほど冷やしてみた。
そうするといい感じで食べられて、家族みんなが「おいしい」「おいしい」と次々口にし、オヤジとしては面目を保つことができた。
実家での最終日の自由時間が30分ほどしかなかったので、揖斐川町のみわ屋まではとても行けず、「こめどら黒胡椒バター」は買って帰れなかった。実家から車で10分で行ける伊吹堂の一択になってしまったわけだが、「揚げパン」と「池田のやま」を大人買いして、お土産とすることができた。
こうしたジャパニーズスイーツが、これからしばらく食べられないのが本当に寂しい。
谷田商店の「ニッキ寒天」 [地域愛]
長期の里帰りで味わった地元スイーツの紹介、その第3弾は、谷田商店の「ニッキ寒天」だ。
浅めのアイスクリームカップにピンク、イエロー、グリーンに色付けされた寒天が充填されているだけのシンプルなパッケージングなのだが、その商品名が示す通り、ニッキが入っているので食べるとさっぱり感が味わえる。
谷田商店HPによると、ニッキ寒天が商品化されたのは1970年頃だという。昔、少学校のプール通いの後、ちょっと疲れたという時のおやつとして、よく食べていたのを思い出す。ちょうど売り出した頃に僕らは小学生だったということだ。母に聞くと、夏場の農作業の後、冷蔵庫で冷やしたニッキ寒天を食べるとさっぱりするという。
ついでに言うと、元々母は岐阜県揖斐川町市場の出身で、その実家は谷田商店から近かった。だから、実家に初孫の僕を連れて帰った際に、僕が爺ちゃん婆ちゃんからご馳走になったのもニッキ寒天だった。
谷田商店は、ニッキ寒天だけでなく、こんにゃくでも有名だ。海外駐在する時に現地でこんにゃくを食べたいということも時々あるので、赴任の際に谷田商店でこんにゃくの素を買って現地に持って行ったこともあった。
そんな谷田商店、今は社屋が移転して、隣の池田町にある。伊吹堂と同じパターンだ。伊吹堂は店舗販売をしているから街道筋に移転するのは致し方ないのだが、谷田商店の場合は、工場が移転したようだ。
ではどこでニッキ寒天を購入できるかというと、道の駅・池田温泉のJAいび川農産品直売所。ということは、JAいび川の農産品特売所なら、どこでも売られている可能性はあります。新型コロナウィルス感染が終息したら、是非お越し下さい。
浅めのアイスクリームカップにピンク、イエロー、グリーンに色付けされた寒天が充填されているだけのシンプルなパッケージングなのだが、その商品名が示す通り、ニッキが入っているので食べるとさっぱり感が味わえる。
谷田商店HPによると、ニッキ寒天が商品化されたのは1970年頃だという。昔、少学校のプール通いの後、ちょっと疲れたという時のおやつとして、よく食べていたのを思い出す。ちょうど売り出した頃に僕らは小学生だったということだ。母に聞くと、夏場の農作業の後、冷蔵庫で冷やしたニッキ寒天を食べるとさっぱりするという。
ついでに言うと、元々母は岐阜県揖斐川町市場の出身で、その実家は谷田商店から近かった。だから、実家に初孫の僕を連れて帰った際に、僕が爺ちゃん婆ちゃんからご馳走になったのもニッキ寒天だった。
谷田商店は、ニッキ寒天だけでなく、こんにゃくでも有名だ。海外駐在する時に現地でこんにゃくを食べたいということも時々あるので、赴任の際に谷田商店でこんにゃくの素を買って現地に持って行ったこともあった。
そんな谷田商店、今は社屋が移転して、隣の池田町にある。伊吹堂と同じパターンだ。伊吹堂は店舗販売をしているから街道筋に移転するのは致し方ないのだが、谷田商店の場合は、工場が移転したようだ。
ではどこでニッキ寒天を購入できるかというと、道の駅・池田温泉のJAいび川農産品直売所。ということは、JAいび川の農産品特売所なら、どこでも売られている可能性はあります。新型コロナウィルス感染が終息したら、是非お越し下さい。
みわ屋の「こめどら黒胡椒バター」 [地域愛]
岐阜県揖斐川町の揖斐の市街地にある和菓子店「みわ屋」は、ここ数年、里帰りするたびに職場へのお土産を買ったりするのに使って来た定番のお店である。春日のお茶を使った「ほうじ茶クッキー」でハマり、その後「ほうじ茶プリン」や「ほうじチャイ饅頭」など、新登場したメニューも軒並み試してきた。地域おこしにも熱心なお店で、近所の揖斐高校の生徒さんとのコラボで開発した3種類のクッキー「信長との約束」は、その開発ストーリーも考えると素通りしづらい、買って応援したくなるようなアイテムだ。
さて、そんなみわ屋の商品の1つ、岐阜産米ハツシモを使ったどら焼き「こめどら」に、新たに「黒胡椒バター」味というのが加わったのを知ったのは、昨年12月に父の容態悪化を初めて聞き、妻と長男と3人で帰省した時だった。約10日間の実家滞在を終え、妻と僕がマイカーで東京に戻るのに先立ち、お決まりとなったみわ屋でのお土産買い出しに行った際、その存在を知って試しに買ってみることにした。日持ちしない、買ったその日のうちに食べてしまわなければならないそのどらやきを、帰りの車中で食べた感想は、「独特のクセになるおいしさ」だった。
餡子とバターは結構相性がいいと思うが、こんなに中にしっかりとしたバタースライスを挟み込んだどらやきは初めてだ。さらに、これにピリッとした胡椒が加わり、一瞬の刺激が舌を通り過ぎる。こんな味は今まで経験したことがない。ただでもどらやきは好きだが、こめどら黒胡椒バターはちょっと病みつきになりそうだ。
さて、そんなみわ屋の商品の1つ、岐阜産米ハツシモを使ったどら焼き「こめどら」に、新たに「黒胡椒バター」味というのが加わったのを知ったのは、昨年12月に父の容態悪化を初めて聞き、妻と長男と3人で帰省した時だった。約10日間の実家滞在を終え、妻と僕がマイカーで東京に戻るのに先立ち、お決まりとなったみわ屋でのお土産買い出しに行った際、その存在を知って試しに買ってみることにした。日持ちしない、買ったその日のうちに食べてしまわなければならないそのどらやきを、帰りの車中で食べた感想は、「独特のクセになるおいしさ」だった。
餡子とバターは結構相性がいいと思うが、こんなに中にしっかりとしたバタースライスを挟み込んだどらやきは初めてだ。さらに、これにピリッとした胡椒が加わり、一瞬の刺激が舌を通り過ぎる。こんな味は今まで経験したことがない。ただでもどらやきは好きだが、こめどら黒胡椒バターはちょっと病みつきになりそうだ。
伊吹堂の「揚げパン」 [地域愛]
3月下旬からゴールデンウィークまで、岐阜に里帰りする機会が多かった。最初は父の具合を見るためだけの数日間の滞在の予定だったが、その間に父が亡くなったことで滞在期間が延び、その後も相続やら名義書き換えやらの手続で、二度にわたって東京と岐阜の間を往復している。(…などと書くと、緊急事態宣言のさなかに何やってんだとお叱りを受けそうだが、こと最後の里帰りについては、後ろが決まっている僕にとって、緊急かつ必要な帰省なのだ。)
現時点で二度の帰京を経験しているわけだけれど、その都度東京の家族へのお土産で購入しているのが、地元・伊吹堂(岐阜県揖斐郡池田町八幡)の「揚げパン」である。5切れ入り1パック540円で売られていて、賞味期限は当日のみ。揚げたてのサクサク感が残り、かつ中のあんこは少し甘さを抑えめにして何かお酒が使われている。
この地域に昔からある伝統的なスイーツの1つが大垣の金蝶園饅頭で、ほんのり酒の香りと味わいがあるが、伊吹堂の揚げパンに挟まれた餡子にも、それに近い味がする。
現時点で二度の帰京を経験しているわけだけれど、その都度東京の家族へのお土産で購入しているのが、地元・伊吹堂(岐阜県揖斐郡池田町八幡)の「揚げパン」である。5切れ入り1パック540円で売られていて、賞味期限は当日のみ。揚げたてのサクサク感が残り、かつ中のあんこは少し甘さを抑えめにして何かお酒が使われている。
この地域に昔からある伝統的なスイーツの1つが大垣の金蝶園饅頭で、ほんのり酒の香りと味わいがあるが、伊吹堂の揚げパンに挟まれた餡子にも、それに近い味がする。
『にっぽんの美しい民藝』 [地域愛]
内容紹介【コミセン図書室】
日本各地の民芸館・有名店を旅しながら、民藝の世界を紹介する本。日本民藝館からはじまって益子、盛岡、会津、松本、南砺、京都、丹波、倉敷、出雲、八女、読谷……など各地域の代表的な手仕事を紹介します。各スポットでは、民藝品の特徴や歴史を紹介。さらに柳宗悦や濱田庄司、芹沢銈介、丸山太郎、河井寛次郎、吉田璋也、バーナード・リーチ、外村吉之介などの民藝同人のゆかりを解説しています。旅で役立つガイドとして使うのはもちろん、民藝の入門書としても楽しめます。
コミセン図書室に本を返却に行くと、ついつい次の本を目いっぱい借りてきてしまう。以前は上限3冊だったのが4冊に緩和され、貸出期間は2週間と変わらずなので、自ずと借りようとする本の中に週末読書用の小説を入れたり、ページをパラパラめくるだけで読んだ気になれるガイドブックのような本を入れたりと、年初に立てた誓いにそぐわない本を選択してきて、それに時間を取られる。
しかし、これまでの僕の本の選択の傾向との関連性が全くないかというとそうでもない。例えば、昨年前半、僕は「民藝」や「アーツ&クラフツ運動」をテーマにして何冊かの本を読んだことがある。さすがに柳宗悦の著書を読むところにまでは至らなかったが、これからの仕事との関連で、和紙作りや竹工芸についてはもう少しハンズオンで知っておきたいと思う気持ちもあり、それらを扱っているような民藝館や民藝品のお店には、足を運んで匿名の人々が製作した作品の数々を実際に見ておきたいと思っている。
もちろん、新型コロナウィルス感染拡大が収束したらという条件付きだし、自分とあまり縁もゆかりもない地方にまで出かけて行ってまで見たいという気持ちもない。せいぜい、東京近辺と実家のある岐阜周辺、さすがに東北や北陸、京都・大阪あたりに足を運ぼうとはなかなか思わない。
聖地で鑑賞、『聲の形』 [地域愛]
昨年10月にご紹介した『聲の形』、今回の一時帰国中に里帰りした岐阜県大垣市の映画館でまだ1日1回上映されているのを知り、かなり慌ただしい日程の中、なんとか時間をひねり出して見てきた。今回の一時帰国中の土産話の1つである。
実際に映画を見てみると、大垣市民病院とか、養老の滝とか、養老天命反転地とか、水門川とか、見慣れた風景が出てくる。ちょっと離れるけど、JR岐阜駅前ロータリーとか、長島スパーランドとかも登場する。大垣の映画館が今でも上映している意味がよくわかるし、これを見て記憶を確認した後で、「聖地巡礼」に出かけるのもいいかも。
少し前に、日本テレビのZIP!で、養老天命反転地がSNSを通じて観光客に人気だと報じていた。20年以上も前にオープンし、デザイナーは既に他界している天命反転地が今さら何故スポットが当たっているのか目を疑ったが、映画『聲の形』を見てはっきりわかった。この映画で将也と硝子が2人で出かけたスポットの1つが天命反転地で、観光客が詰めかけたのは、「聖地巡礼」の一環であったということなのだ。
勿論、玄関口である大垣駅も券売機前が映画には登場するが、改札口を抜けた連絡通路の窓にも、デカデカと『聲の形』のポスターが貼ってあった。
聖地で見る映画も、なかなかおススメです。
実際に映画を見てみると、大垣市民病院とか、養老の滝とか、養老天命反転地とか、水門川とか、見慣れた風景が出てくる。ちょっと離れるけど、JR岐阜駅前ロータリーとか、長島スパーランドとかも登場する。大垣の映画館が今でも上映している意味がよくわかるし、これを見て記憶を確認した後で、「聖地巡礼」に出かけるのもいいかも。
少し前に、日本テレビのZIP!で、養老天命反転地がSNSを通じて観光客に人気だと報じていた。20年以上も前にオープンし、デザイナーは既に他界している天命反転地が今さら何故スポットが当たっているのか目を疑ったが、映画『聲の形』を見てはっきりわかった。この映画で将也と硝子が2人で出かけたスポットの1つが天命反転地で、観光客が詰めかけたのは、「聖地巡礼」の一環であったということなのだ。
勿論、玄関口である大垣駅も券売機前が映画には登場するが、改札口を抜けた連絡通路の窓にも、デカデカと『聲の形』のポスターが貼ってあった。
聖地で見る映画も、なかなかおススメです。
タグ:大垣






















