『アパレル・サバイバル』 [シルク・コットン]
内容(「BOOK」データベースより)
消費者の「クローゼット」を支配せよ!アマゾン「プライム・ワードローブ」、ZOZO「おまかせ定期便」、メルカリが変えた中古の意味…10年後の勝者が見通す壮大な戦略!
刊行されて2ヵ月少々、日経新聞の書評で取り上げられたのもつい最近という1冊を、市立図書館で順番待ちわずか1回のみで借りることができたのはラッキーだった。この手のアパレル業界情報を扱った本は2017年に出ている『誰がアパレルを殺すのか』以来だが、時々読んでキャッチアップしておかないといけないとつくづく感じる。それくらいはやりすたりが激しい。
本書において、著者は、アパレル業界のトレンドは10年ごとに新しいイノベーションが起こり、欧米のおよそ10年後を日本は追いかけてきているとの仮説を提示、2008年のファストファッションブームの日本上陸から10年が経過した2018年は、日本のファッション流通の新たなパラダイムシフトの年になると予測している。この仮説によると、これまでの10年間に欧米で起きてきたことを見れば日本で次に起きることがおよそ予測可能だとする。
1つは、ベーシックカジュアルアパレルSPA(アパレル製造小売り)やファストファッションSPAを下回る「さらなる低価格化」、2つめはチェーンストアによる電子商取引化の流れ、3つめは、(本書ではあまり深掘りされてないが)アパレル事業からランジェリーとヘルス&ビューティ事業にドメイン変更する流れ、4つめは店舗で無料体験を提供する業態の躍進なのだという。
この中でも本書で中心的な扱いを受けているのは上記2で、欧米の小売業店舗で見られるデジタル化や機械化の流れが、最先端テクノロジーをアピールするものではなく、顧客の体験やストレス解決を最優先にした課題対応型の適応策だと強調する。店舗スタッフの作業軽減に関しては日本の小売店でもセルフレジの取組み等が見られるが、欧米では、来店客の無駄足の軽減、接客待ち、試着待ち、レジ待ちの時間の軽減といった、ユーザーの利便性の向上を主眼として導入されているのが特徴で、著者は、この動きが今後日本でも強まっていくだろうと予想する。
アッサム側のシルクビジネス [シルク・コットン]
国境を越えて広がる野蚕シルクビジネス
Burey business thrives across border
Kuensel、2018年3月28日、Tshering Namgyal 記者(サムドゥップジョンカル)
http://www.kuenselonline.com/burey-business-thrives-across-border/
【ポイント】
サムドゥップジョンカルの街を訪れるブータン人の多くは、インドとの国境を越えてアッサム州ダランガの街まで出かける。目的はブラ(野蚕シルク)の生地を購入すること。この生地は、メチ(Mechey)、コチラパ(Kotsirapa)、グダマ(Gudama)、サムドップジョンカル・ブラ(SJ Burey)などと呼ばれ、自家用、贈答用、いずれのニーズもある。ダランガを訪れる多くのブータン人は東部の人々。
国境沿いのインド側にあるグダマやメラバザールといった街では、ブータンのゴやキラに使えるパターンの生地が生産されている。ショールームを訪れるブータン人の相手をする店主は、流暢なシャショップ語を話す。40店舗ほどが集まる市街地で、生地を扱う卸売業者は6店舗あり、その周辺に加工品を小売りする業者が数店舗展開している。ブラのゴ、キラの価格は1800ニュルタムから15,000ニュルタム。カブニは1500ニュルタムから4000ニュルタムの価格帯だという。
インドの巨額紙幣廃止や物品サービス税(GST)導入の影響は、ブラ取扱業者の間ではあまり感じられていない。ブラに対する需要は堅調で、1店舗当たりの月間売上高は、5万ルピーから200万ルピーにもなるという。店主の1人、ビジュ氏(48歳)は、この地で35年間営業を続けているが、毎日30~50人のブータン人が店舗を訪れ、月50万ニュルタムの売上げがあるという。
Burey business thrives across border
Kuensel、2018年3月28日、Tshering Namgyal 記者(サムドゥップジョンカル)
http://www.kuenselonline.com/burey-business-thrives-across-border/
【ポイント】
サムドゥップジョンカルの街を訪れるブータン人の多くは、インドとの国境を越えてアッサム州ダランガの街まで出かける。目的はブラ(野蚕シルク)の生地を購入すること。この生地は、メチ(Mechey)、コチラパ(Kotsirapa)、グダマ(Gudama)、サムドップジョンカル・ブラ(SJ Burey)などと呼ばれ、自家用、贈答用、いずれのニーズもある。ダランガを訪れる多くのブータン人は東部の人々。
国境沿いのインド側にあるグダマやメラバザールといった街では、ブータンのゴやキラに使えるパターンの生地が生産されている。ショールームを訪れるブータン人の相手をする店主は、流暢なシャショップ語を話す。40店舗ほどが集まる市街地で、生地を扱う卸売業者は6店舗あり、その周辺に加工品を小売りする業者が数店舗展開している。ブラのゴ、キラの価格は1800ニュルタムから15,000ニュルタム。カブニは1500ニュルタムから4000ニュルタムの価格帯だという。
インドの巨額紙幣廃止や物品サービス税(GST)導入の影響は、ブラ取扱業者の間ではあまり感じられていない。ブラに対する需要は堅調で、1店舗当たりの月間売上高は、5万ルピーから200万ルピーにもなるという。店主の1人、ビジュ氏(48歳)は、この地で35年間営業を続けているが、毎日30~50人のブータン人が店舗を訪れ、月50万ニュルタムの売上げがあるという。
にわか勉強、ファッションEC [シルク・コットン]
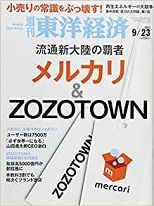 週刊東洋経済 2017年9/23号
週刊東洋経済 2017年9/23号東洋経済新報社、2017年9月19日
Amazon URLはこちらから。
内容紹介(第1特集のみ)
【第1特集】流通新大陸の覇者 メルカリ&ZOZOTOWN
[イラスト図解]メルカリ&ZOZOTOWNが切り開く新大陸
Part1 爆走するメルカリ
創業5年目のメガベンチャー 流通革命児の野望
賢く売り買いするコツ メルカリ徹底活用術
INTERVIEW│山田進太郎●メルカリ会長兼CEO
エリートが大集結 メルカリ経営の強力布陣
独走を止められるか 楽天、ヤフーの追撃策
知らずに使い続けて大丈夫? メルカリユーザー転ばぬ先の杖
Part2 ZOZO未踏の境地
時価総額1兆円を突破 常識破りの成長軌道
手数料3割でも続々出店 強まるZOZOの磁力
INTERVIEW│重松 理●ユナイテッドアローズ名誉会長
INTERVIEW│栁澤孝旨●スタートトゥデイ副社長兼CFO
業界が大注目! ZOZO自社ブランドの勝算
[キーマン4人に聞く]ZOZOTOWN強さの秘訣
ZOZOの背中ははるか先 競合ECは生き残れるか
激変続く流通新大陸 勝ち残りの条件とは
9月、わけあってファッションEコマース、もっと言ってしまえばZOZOTOWNについて少し勉強してみることにした。きっかけは知人のある発言なのだが、そもそもZOZOTOWNの名前は知っていても何をやっている会社なのか全然知らなかったので、その時は知人の話に適当に合わせて頷いているしかなかった。自分の不勉強を恥じて、ちゃんと理解しておこうと思った。
その一環で最初に読んだ本が『誰がアパレルを殺すのか』であった。続いて読んだのは後から紹介する2冊だった。そして、9月に日本に帰った時、羽田空港の売店で見つけたのが週刊東洋経済のメルカリ&ZOZOTOWN特集号だった。多分、僕のような業界人でもない人間がZOZOTOWNを知っておくなら、このぐらいがちょうどいいのではないかと思った。
『繭と絆』 [シルク・コットン]
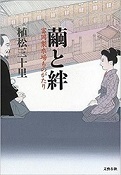 植松三十里著
植松三十里著『繭と絆-富岡製糸場ものがたり』
文藝春秋、2015年8月26日
Amazon URLはこちらから。
内容紹介
世界遺産・富岡製糸場の成立秘話が満載。富岡製糸場の初代工場長・尾高惇忠の娘・勇は、婚約を棚上げして女工になる。明治の日本を支えた製糸業を隆盛に導いた父娘のドラマ。
―――それにしても、早く直らないですかね、ブログのAmazon商品紹介機能。
あれは書籍の紹介するのにものすごく便利だったので長年利用してきたが、9月22日以降機能が使えなくなっており、ソネットからは復旧の時期も明らかにされていない。
その間に読了した本、その前に読了しておきながらブログで紹介するタイミングを逸してここまで来ていた本も、一時帰国して少し時間に余裕があった本邦滞在期間の後半に記事アップしたかったがそれもかなわず、ずっとブータンの新聞記事の紹介でお茶を濁してきた。
しかし、それでもそろそろ限界なので、これからの数回は、書籍紹介も取り混ぜていこうと考えている。
その第1回は、これは読了したばかりの歴史小説。副題にある通りで、富岡製糸場の製糸工女第1号となった尾高勇(おだかゆう)が主人公の話である。尾高惇忠、勇、渋澤栄一、速水堅曹あたりは実在の人物だが、実際に勇とともに入所した初代製糸工女の数名は、いたのかどうかはよくわからない。中の良かった2人の工女は勇の結婚と軌を一にして北海道の開拓使製糸場の教官として赴任しているが、北海道に製糸場は確かに存在したし、明治8年開業というところも事実関係としては合っている。
『誰がアパレルを殺すのか』 [シルク・コットン]
内容(「BOOK」データベースより)
大きな転換期を迎えたアパレル業界。この産業を衰退に追いやった“犯人”は誰か。サプライチェーンをくまなく取材し、不振の真因を、ついに突き止めた!
ベストセラーになったビジネス書を紹介する。元々日経ビジネスの特集記事だったものを、書籍版に改訂したのだそうだ。
衣料品が売れなくなった、業況が悪化している―――これは、親交があるこの業界の方からも会って飲むたびに聞かされる最近の話であった。そういう状況の中で、どこまでCSRを頑張れるのか、業況悪化したらさっさとCSRから手を引くのか、僕には非常に気になるところだが、知人からこの話を聞かされるたびに、まあ一時的なものなのではないか、業況も、悪い時もあれば良い時もあるのではないか、などと安易に考えていたところがあった。
ところが、本書を読んでみると、話はそんなレベルではない、もっと構造的なもので、業界大手が相当ドラスティックに変わっていかないと、退出する企業が続出するのではないかと思うようになった。ショッキングなタイトルに対する著者の答えは、戦後復興期から発展を遂げてきた従来型のアパレル企業が、高度成長期からバブル期に至る過程で得た成功体験から脱却できず、思考停止に陥っているのだと述べている。
逆に、そうした成功体験を経ていない新興企業は、業界の内輪の論理にとらわれず、自由な発想でサービスを展開し、実績を上げているという。衰退したといわれるアパレル産業の中にも、生き残っていける企業はあるというのも著者の強調しているポイントだ。
『蚕の村の洋行日記』 [シルク・コットン]

蚕の村の洋行日記―上州蚕種業者・明治初年の欧羅巴体験 (セミナー〈原典を読む〉 (5))
- 作者: 丑木 幸男
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 1995/07
- メディア: 単行本
内容(「MARC」データベースより)
「帰国の時はおまへを大切に致し候」 蚕の種紙を売りに出かけたイタリアから、こう妻に書き送った上州村の豪農たち。近代のとば口の様々な西洋体験は、人々に何をもたらしたか。
6日(水)、かねてからの念願だった「世界遺産」富岡製糸場に行ってきた。「世界遺産」というのがくっついたお陰で訪問客が増え、なかなか行く機会を見出せずにいたのだが、さすがに海外赴任まで残り時間が少なくなり、前の部署での仕事もひと段落ついて出勤せずに赴任準備に時間が割けるようになってきたので、まさにその赴任準備と称して、富岡まで足を運んだのである。
東京からの一人旅。車で行くのと電車で行くのとでかかる費用を比べて、後者を選択した。但し、目的地にまで辿り着くまでには時間もかかる。行きは朝8時半に最寄り駅から出発し、製糸場到着は正午だった。帰りも同様に3時間半かかった。これだけ時間がかかるわけだから、良い機会なので積読状態だった蔵書を多少でも読み進めようと考え、携行した1冊が『蚕の村の洋行日記』だった。
サブタイトルに「上州蚕種業者・明治初年の欧羅巴体験」とある。このサブタイトルだけ見れば、上州境島村の田島家が代表して欧州にわたり、島村産の蚕種を欧州のバイヤーに直接売った例の話だと容易に想像がつく。この話については橋本由子著『上州島村シルクロード』をブログでご紹介した際に概略説明済みなので併せてご参照下さい。『上州島村シルクロード』は子供向けの読みものとして書かれているので、欧州に渡った人々の現地でのご苦労が物語風に描かれているので理解しやすいが、実際に彼らが残した報告書や現地から出した書簡などの史料が直接引用されてるわけではない。そこを補っているのが『蚕の村の洋行日記』だ。
この本には、そうした史料の引用がかなり頻繁に出て来る。お陰で、1879年(明治12年)の第1回直輸出における派遣で、田島弥平、信、弥三郎の3人は西回りの航路ではなく、東回りの航路を使い、先ずサンフランシスコで上陸して、大陸横断してナイヤガラ、ニューヨーク見物など行っていることや、こんなルートを使えるくらいだから、相当な所持金を持っての豪遊だったことなどが浮かび上がってくる。
『蚕:絹糸を吐く虫と日本人』 [シルク・コットン]
内容(「BOOK」データベースより)
世界一の生糸輸出国だった近代の日本。お金を運んでくれる虫と、私たちはどのように暮らしたのか。養蚕が生み出した文化と芸術を、気鋭の民俗学者が掘り起こすノンフィクション。
2012年のはじめ、僕はインドにおける日本とインドの蚕糸業技術協力の歴史をまとめて、1冊の本にした。その後、南インドの蚕糸業地域にはJICAの青年海外協力隊の隊員の方々が派遣されるようになり、隊員の皆さんは僕の本を参考にしながら現地で活動されているそうだ。僕の次の赴任国はインドじゃないけれど、地理的にはインドには近くなることから、機会があれば南インドをまた訪問して、僕がインタビューした養蚕農家の方々は今どうされているのか、追跡調査もしてみたいし、本を書くにあたって紙面の関係上あまり触れられなかった製糸や織物の話について、もう少し調べてみたいと思っている。勿論、青年海外協力隊の方々と交流させていただけるのも楽しみだ。
次に南インドを訪れる機会がいつ訪れるのかはわからない中ではあったものの、本を出してからの4年間、僕が意識してきたことはむしろ日本の蚕糸業の歴史をもっと勉強しておくことだった。本を書いたおかげで、国内ではいろいろな方々とのつながりができた。そうした方々に誘われて、行ってみた先では今まで知らなかった新たな発見もあった。イザベラ・バードの『日本奥地紀行』を読めば東北地方で養蚕が相当広い地域で行われていたことがわかるし、その名残が後に宮本常一によって改めて紹介されている。宮本の著作には東北に限らず、全国の農村で養蚕が普通に行われていた様子が描かれている。
養蚕自体が主目的でなかった数々の本の中から養蚕のピースをかき集め、それらを組み合わせることで1つの絵図を頭の中で作っておきたい――そういう思いからこつこつ続けていた勉強は、次に南インドを訪れて、特に若い協力隊員の方々との交流の中で、少しは役に立つこともあるかもしれない。また、僕が今度赴任する予定の国にも、産業と言うには規模も小さいけれど、養蚕や絹織物の産地がある。そういう生業を見る際の物差しとして、日本は昔どうだったのかを知っておくことは大事だと思っている。
さて、本日ご紹介の1冊は、その蚕糸業をコアにした、ど真ん中直球勝負の本である。昨年ブログで紹介した、『「日本残酷物語」を読む』の著者、新進気鋭の民俗学者・畑中章宏氏の新著だ。宮本の著作を相当細かく追っかけていれば、バードや宮本自身の蚕糸業に関する記述を拾い出して、「カイコ」や「絹」を主題に1冊の本にすることがあっても何ら不思議ではない。僕が頭の中でやろうとしていたことを、こうして文章化して世に出すというのは、たいへんありがたいことだし、一方で羨ましいことでもある。
『事典 絹と木綿の江戸時代』 [シルク・コットン]
内容(「BOOK」データベースより)
江戸時代、中国船やオランダ船により絹や木綿がもたらされ、多くの種類が流通した。縮緬、さらさなどの舶来の絹・木綿の語源、国産の絹・木綿の原系や染色などを解説する近世における織物の全容を解明した労作。
以前、『苧麻・絹・木綿の社会史』をご紹介する中でも触れた、山梨県立博物館の企画展「天の虫のおきみやげ~山梨の養蚕信仰」、展示は明日までということで、行けるとしたらこの日しかないと考え、早くから有給休暇の申請を出していた25日(木)だったが、前夜から次男が熱を出し、妻がその日に次男を病院に連れて行くことになり、休暇なのに山梨まで出かけるとはなにごとかと苦言を呈せられたこともあって、断念せざるを得なくなってしまった。それだったら、代わりに近場で少しぐらいはシルクのことを考える時間を作ろうと思い、市立図書館に2時間ほど立ち寄って、館内閲覧限定だった書籍を流し読みするのに充てた。
この本、既に絶版になっていて、売りに出ている中古本はなんと5500円もする。それだけ払っても購入する価値のある本かどうかはわからないので、先ずは近場で所蔵している図書館を探し、ざっと目を通してみて買うかどうするかを判断しようと思っていた。そう思ってから2年以上放置状態だったのだが、先月から継続中の、読書メーターで「読みたい本」リストに挙げていた本の圧縮作業の一環として、4月までに片づけてしまおうと思っていたことの1つであった。
まあ、事典ですので。さらっと流し読みして、おおまかにどんなことが書かれているかをチェックして取りあえずは良しということにさせて下さい。率直に言って、まえがきもなくいきなり本文に入ってしまうのに度肝を抜かれ、読んでてもああこれは事典なんだというのを再認識させられた。江戸時代に出回っていた糸と織物の種類を、輸入もの、国産とに分類し、その織り方、染め方等がざっと列挙されてる感じである。時おりエピソードが入っていたりもしないこともないが、はっきり言ってしまえばやっぱり事典だ。
ただ、絹と木綿の両方に言及があるのはありがたいことである。強いて1つだけ印象に残ったことを触れておくとすると、既に江戸時代にはインドから更紗(綿織物の1種)が輸入されていたとか、新たな発見だった。
必要があればその都度また図書館で閲覧して、記載内容を確認できればいいだろう。5500円も払う価値のある本だとは正直あまり思えなかった。同じ江戸時代の絹・木綿を扱っているという点では、前述の『苧麻・絹・木綿の社会史』の方がはるかに面白いし、その本は既に入手済みだ。
さて、こうして本書の内容確認をやってお茶を濁した25日であったが、肝心の次男の容態はというと、その日の朝には既に熱がある程度まで下がり、午後には起きて自宅でプラプラしていた。「こんなことなら山梨行ったら良かったのにね」とほざいた妻の首を絞めたくなった(苦笑)。
『蚕の城』 [シルク・コットン]
内容(「BOOK」データベースより)
日本の遺伝学は蚕(絹織物産業)から始まった!明治日本の近代化の礎として世界遺産に登録された富岡製糸場と絹産業遺産群。その一つ、荒船風穴に代表される蚕の種(卵)を保存する技術は3・11以降、遺伝学研究にとって非常に重要なものとなっている。カイコをめぐって発達した産業と学問の、黎明期から現在まで明治以来、連綿と続く、カイコの遺伝学を中心に追う。
このところ、珍しくも「蚕(カイコ)」と名の付く新刊本が出てきている。富岡製糸場と上州の絹産業遺産群が世界遺産登録されたことが大きいのだと思う。放っておいたら忘れ去られてしまう日本の文化や産業の遺産にこうして光が当たるのは良いことだ。
僕も少し前にカイコのライフサイクルを勉強し、それを生かして産業として発展させた蚕糸業の歩み自体の理解も深めた。特に製糸の工程については、日本の近代化を支えた明治から昭和初期の群馬や岡谷の様子を調べ、勉強もしてきたつもりだ。ところが、理解困難でなかなか触れられなかった養蚕の一側面がある。それが系統保存と育種である。
そもそも遺伝学なんて中学生の頃にメンデルの法則を少しかじったぐらいだし、一時期わりとよく見ていた競馬でも、サラブレッドの血統について言われていることはよくわからなかった。近代産業としての養蚕が成立する以前なら、自家で掃き立てたカイコの中から形質の良さそうな繭を選んで成虫を羽化させ、交配して次の種を得るような自家再生産をやってたんだろうと漠然と思っていた。しかし、質が一定の繭を大量に生産する必要が生じた近代の蚕糸業はそんなわけにいかないから、品種の改良とか行いつつ、一定品質の種を大量生産する仕組みも整えられていったに違いない。
しかし、そんな掛け合わせの妙による育種や、その系統を長期間保存して絶滅しないよう備える技術など、特別な知識と技術が必要な世界で、僕らのにわか勉強ではとうてい太刀打ちできない話のように思えてならない。現に、この部分については一般読者向けにわかりやすく書かれた本というのが意外と少ない。カイコの飼育に関してはいっぱい本があるのに…。
ところが、そんなジャンルにあえて切り込んだルポライターがいた。
『苧麻・絹・木綿の社会史』 [シルク・コットン]
内容(「BOOK」データベースより)
前近代の日本人の三大衣料原料であった苧麻・絹・木綿。その生産はどのように行われ、民衆の暮らしとどう関わったのか。三本の糸を手繰りながら、これまで見えなかった民衆の生活史・社会史像を独創性豊かに織り出す。
少し前に別の記事で、「海外赴任する前に富岡製糸場は見ておきたい」という趣旨の発言をしたことがあった(こちらの記事参照)。その実現は3月以降のお楽しみということにして、今どうしても行きたいのは、実は山梨県立博物館の企画展『天の虫のおきみやげ-山梨の養蚕振興』だったりするわけだ。こちらは展示期間が今月いっぱいまでなので、平日に会社休んで早く行きたいと思っている。そうなると、懸案だった『富岡日記』は後回しで、その前に読んでおくべき積読の書を片付けることからスタートせねばなるまい。
日本の歴史学の泰斗ともいえる永原慶二の著したこの本は、購入してから積読状態での放置が1年以上に及んでいた。海外赴任の日までに積読状態の本をできるだけ減らすという至上命題のため、僕は山梨県立博物館行きを誓ってすぐに、この本を読むのに取りかかった。それでもなかなか読み進めることができず、この1週間でなんとか勢いをつけ、読み切ることができた。
購入した動機は、1冊の本の中で、絹と木綿が扱われてることに尽きる。これまで、絹は絹、木綿は木綿で、日本の歴史の中でどこからどのように登場し、普及していったのかを解説してくれる本は存在していた。どこのどのような本ではどのように描かれてるか、そうした相場観は何となく養成できたように思う。ところが、視点を変えてそこに暮らす人々の衣服として捉えた場合、それを絹、木綿と素材別で切り分けてしまっては、日本人の暮らしがどのように変わっていったのかをダイナミックに捉えることができない。
永原氏の著書の1つに『新・木綿以前のこと』(中公新書、1990年)がある。柳田國男の『木綿以前のこと』になぞらえてこんなタイトルになったのだろう。でも、この本に関するアマゾンのレビュー欄を読むと、この本に書かれているのは主に「木綿以後のこと」だとの批判がある。「木綿以前のこと」にはあまり触れられていない。著者もこの題は気が進まなかったが、編集者に強引に言われてこうなったのだという。著者の心の中にはずっとそんなわだかまりがあったのだろう。晩年になると、「木綿以前こと」と「木綿以後のこと」を統合して、日本の社会の変遷を、衣料の素材の変遷から、捉えようという試みに着手し、本書の二校まで進んだ段階で、他界されるに至ったのだそうだ。










